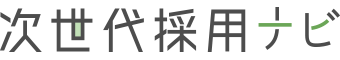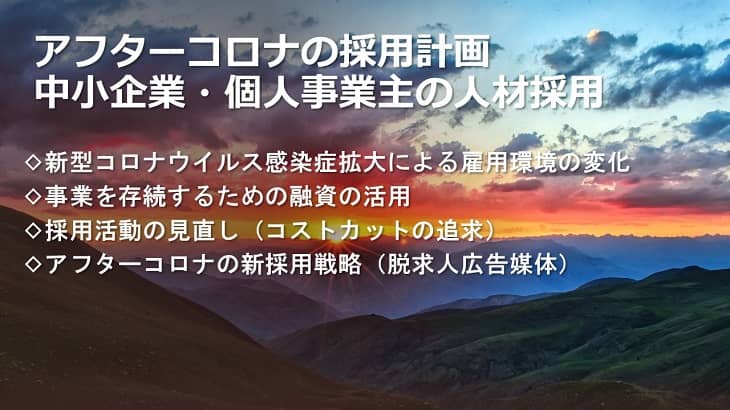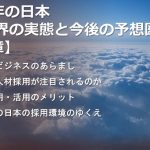2020年に入り新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を奮い、今も尚その影響は大きく、私たちの生活を脅かし続けています。新型コロナウイルス感染拡大の抑制・防止を図った結果、経済活動・消費活動が落ち込んでしまい、リーマンショックを越えるともいわれる世界的な経済打撃を受けています。
その影響により国内においては、倒産・廃業を余儀なくされる、企業や店舗が増えています。現在は、政府による助成金の支給などもあり、何とか運転資金の工面が出来ている事業所も、このような状況が続けば事業存続が危ぶまれることは、想像に難くありません。
事業をどうにか継続させるために、人件費カットやアルバイト・パートの契約解消に踏み切った事業所も多いかと思います。一旦は事業を縮小し、様子を見ることも永続的に事業経営をしていく上で重要な判断です。
しかしながら、今後事業を再建し、売上を戻していくためには、また新たな人手が必要となります。ところが、新型コロナウイルス感染症拡大は私たちの生活を一変させてしまいました。仕事の価値観の変化、労働人口の減少などが起きる中、今まで通りのやり方で果たして人材採用は成功するのでしょうか。
本記事では、アフターコロナに向けた今後の採用の在り方について解説をしていきます。
特に、中小企業の経営者様や個人事業主の方は、既存の方法の見直しや、新たな気づきにして頂けたら幸いです。
多くの業界に大打撃を与えたコロナウイルス
新型コロナウイルス関連倒産発生件数の推移
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国内の消費活動が大きく減少した結果、多くの業種で昨年同時期比較で売上が大幅に減少しています。
政府の試算によると、2020年度の経済規模はおよそ40兆円、GDP全体の7.3%縮小すると見られています。オリンピックの開催時期が見送られ、インバウンド訪日観光客も渡航禁止となった結果、経済活動の冷え込みは回復しきれず、雇用にも多くの影響が出ています。
特に外食産業、観光・宿泊業、服飾小売り製造・販売、交通関連業界の落ち込みは大きく、廃業を余儀なくされた店舗・企業も増えています。10月中旬の時点で600件以上が新型コロナウイルス関連倒産となっています。
2020年10月に入り、倒産件数はやや鈍化していますが、その要因としては、政府の助成効果が大きいとみられています。
しかし、当面の資金繰りが出来たとしても、今後事業が黒字にならなければ、廃業・倒産件数は、これから更に増加する懸念があります。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響による解雇・雇い止めの人数
厚生労働省による2020年9月24日の発表では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による解雇・雇い止めの人数が累計60,439人となり、6万人を超えたと明らかにしました。10月以降も、さらに加速度的に増加しており、雇用情勢の悪化に歯止めがかかっていない状況です。
政府の支援も根本的な解決にはならず
政府は、消費活動を後押しするため、Go Toキャンペーン(Go Toトラベル、Go Toイート)で、宿泊・観光施設、飲食店事業者を支援しています。キャンペーンのおかげもあり、観光地では久々に満室予約になった施設も出るなど一定の成果も表れています。
しかしながら、コロナウイルスは依然として終息兆しを見せていません。
足元では、新規感染者数や、死亡者数が以前に比べて落ち着いるため、人々の危機意識も徐々に薄れている印象もありますが、現在もクラスター(集団感染)が各地で報告されるなど、国民一人一人の危機管理意識が求められる状況です。
もし、事業者側が対策を甘くみてしまえば、自店舗でクラスター(集団感染)発生の危険もあり万が一そのようなことが起きてしまえば、売上の低迷は元より、クラスターが発生した店舗というイメージが根付き、その後の信頼回復は難しくなります。
新型コロナウイルスから命を守らなければならない。しかし、経済は止めてもならない。という相反する矛盾を抱えながら、ウイズコロナ・アフターコロナ時代を生き抜いていかなければなりません。
事業を存続させるために、融資という選択肢
未曾有の経済危機と発展した新型コロナウイルス感染症拡大ですが、今後も見えない恐怖と戦い続ける必要があります。
売上が減少している中、当面の運転資金を確保するためには、国の助成を受けない手はありません。全ての助成金制度を理解し、出来る限りのことは行えているか、今一度確認しましょう。
特に確認すべき助成金はこちらです。
・雇用調整助成金(雇用を維持するために休業手当の一部を支給)
・持続化給付金(新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している場合に支給)
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスへの転換事業、テレワーク環境の整備などに対して利用可能)
・小規模事業持続化補助金(商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人に対して支給)
その他、「次世代採用ナビ」では新型コロナウイルス対策の助成金・融資関連情報の発信を続けています。ぜひ詳細内容をご覧ください。
「新型コロナウイルス対策の助成金・融資」情報一覧はこちら
採用活動の見直し
求人広告媒体の成果を分けるポイントを理解する
助成金や人件費カットで、一旦の資金繰りが出来たとしても、毎月掛かる固定費や、既存社員の給与の支払いを維持するためには、売上確保は必要となります。
売上を増やすためには、人材確保が必要です。多くの企業では、人材確保=求人広告媒体の掲載を思い浮かべるのではないでしょうか?
しかしながら、コロナとは関係なしに、労働環境は年々厳しくなっています。実際にコロナ直前の時期には、費用を掛けて求人広告媒体に掲載をしても、応募すらないという声も多くありました。
コロナショックにより転職希望者が増え、応募が増えるだろうと考えるかもしれませんが、実際は容易ではありません。国内の労働人口は年々減り続けているため、特に中小企業における採用活動は非常に難しくなっています。
求人広告媒体で成果を生み出すには、公式があります。
求人広告媒体の成果=企業力(規模・ネームバリュー・風土)×募集条件(給与・待遇)×広告企画力(掲載頻度・露出度・広告内容)
例えば、ネームバリュー(企業力)があり、給与が高く休みが多い企業(募集条件)は、それだけでも応募が集まりやすいため、1回求人を出してしまえば採用にまで繋がる可能性が高いです。
しかし、自社に明確なネームバリューがなく、条件も大手ほど高く出せないとなると、残すは広告企画力で賄うしかありません。
広告企画力=掲載頻度×露出度×広告内容
そのため、掲載頻度を増やしたり、露出を高めるために大きな広告スペースへの掲載や、複数の求人媒体に掲載するといった方策をとります。

広告内容に関しては、求人広告会社の担当者によって差が大きい部分で特に注意が必要です。知識・経験が豊富な担当者であれば自社らしさや魅力が詰まった内容に仕上がりますが、知識・経験が浅い担当者の場合は、他の企業と全く差別化されていない無味乾燥な内容に仕上がります。当然、後者は効果が出ません。
そして、何より問題なのが、基本的に掲載企業側は求人広告会社の担当者を選べないということです。「求人広告のプロが作った原稿ならどれも同じような効果が見込めるだろう」と考えては危険ということです。
なぜなら、求人広告会社は企業の掲載費用で儲けているため、効果は二の次となりがちです。もちろん、効果にこだわるからこそ、クライアントとの良好な関係が築け、長期的な売上を上げている広告会社や担当者もいます。
しかし、仕組み的には、効果が保証されるわけではないので、ある意味広告内容の良し悪しは、運とも言えます。
コストカットの追求。求人広告会社任せにしない
ここまで、企業力・募集条件が乏しい企業(主に中小企業)が求人広告で効果を生み出すためには、2つの課題があることが理解いただけたかと思います。
課題1 露出を増やす→掲載費用が掛かる
課題2 広告内容で魅力を伝える→担当者によって差がある。ノウハウ蓄積に時間が掛かる。
どちらも費用と時間というコストが掛かります。
仮に、運よく良い担当者に巡り合えたとしても、異動や退職で別担当に変更することはしばしば起こります。すると、担当者と培ってきた時間コストは無駄になります。(引継ぎも不十分である場合が多い)
採用費用を極力抑え、時間コストを無駄にしないためにどうすれば良いでしょうか?
それは、求人広告会社を通さず、自社で求人広告の掲載から採用活動管理を一気通貫で行うことです。
求人広告会社の有料媒体を使わなければ広告費用は一切かかりません。
また、自社で求人掲載・採用活動管理をすることで、採用活動の流れがわかるようになり、社内で独自の知見が溜まります。自社内であればマニュアル作成や、情報共有も容易にできるため、課題の発見や対策の検討がスピーディになります。
続いては具体的な対策について解説していきます。
中小企業、個人事業主の新採用活動
自社ホームページの活用
自社でホームページに採用情報ページをお持ちの企業・店舗事業者も多いと思います。しかし、ただ単に採用ページが存在しているというだけでは、ほとんど効果は見込めません。
実は、採用ページを求人広告媒体のように、活用することが可能です。それを「オウンドメディアリクルーティング」といいます。
具体的には、「Indeed」、「Googleしごと検索」、「求人ボックス」といった、求人専門の検索エンジンに、検索ヒットされるように、採用ページの掲載情報を整えること(SEO=検索エンジン最適化)です。
また、採用ページに、「Googleアナリティクス」のようなアクセス解析ツールを導入することで、どれくらいのサイトアクセスがあるか、応募があるかといったことを分析することが可能です。
実際に、オウンドメディアリクルーティングで採用が上手くいっている会社は、採用ページにどれくらいアクセスがあり、そこから何件応募があるか分析を行い、求人広告費用を一切掛けずに採用活動を行っています。
SNSのフル活用
求職者と接点をとるポイントは、求人広告・採用ページに限りません。
お店の前に張り紙を貼るように、たまたま自社の採用情報を見つけてくれた人がいつでも応募できるように、ユーザーと接点がある部分には全て募集情報を入れることをおススメします。
例えば、
・Googleマイビジネス
・Twitter
・Facebook
・Instagram
といったSNSツールは全て活用しましょう。
自社採用ページに飛べるように、URLのリンクを貼るだけでも構いません。直接見てくれた人が応募しなかったとしても、知人や友達にシェアをすることもあります。
Googleマイビジネス、SNSの活用については、こちらの記事もご覧ください。
Googleマイビジネス登録で店舗情報が検索結果一覧に!
集客UPに最も効果的なSNSをお教えします!|徹底比較
また、自社採用のページが1つあるだけで、従業員の方も、紹介しやすいでしょう。自分の言葉で自社の魅力を伝えきるのは、難しいですが紹介ページのシェアならスマホの操作一つでできます。
既存社員による紹介採用を「リファラル採用」といいます。リファラル採用については、こちらの記事もご覧ください。
社員全員が人事に?「リファーラル採用」を徹底解説|次世代採用の新常識
採用管理システム(ATS)の導入
メインとなる採用ページを1つ作り、そこへの導線としてSNSを中心としたメディアにリンクを貼ることをお伝えしました。
「採用ページを作るのは大変。」「うちにはWEBサイトを作れるエンジニアやデザイナーがいない。」「外注したら費用が高い」というお悩みもあるかと思います。
そこで、おすすめなのが、採用管理システム(ATS)を導入することです。採用管理システムを活用することで、簡単に自社の採用ページを作れるだけではなく、応募状況、選考状況の可視化をすることが可能です。
また、その時採用に至らなかった人材をストックし、別の機会にオファーを掛ける(タレントプール)ことも可能です。
yoiwork採用管理で簡単求人作成
採用管理システムは既に多くの会社でサービスを展開していますが、ここではyoiwork採用管理についてご紹介します。

yoiwork採用管理の特徴
- 永久無料で使える
- 採用管理が自動化できる
- 日本人だけではなく、外国人採用にも使える(多言語機能)
特に、国内労働人口は減少の一途を辿ります。
国立社会保障・人口問題研究所によると、現在から2045年にかけて、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)の割合が増加するのは南関東のみと予想されています。特に北海道、北関東、四国は高齢化がより深刻であり、人口の9割以上を65歳以上が占めるという予想もあります。
そのため、今後日本人だけで人材を確保することは難しくなります。外国人材を積極的に受け入れていくことが求められます。外国人労働者が増えるということは、在日外国人がお客様であることも増えるということです。つまり、外国人との共存は今後当たり前になるということです。
現在国内の採用サービスの多くは、未だ日本人求職者を対象としているものがほとんどであるため、外国人採用に特化し、かつ無料で使える採用管理システムはyoiwork採用管理のみとなっています。
まとめ
従来の求人広告会社任せの採用を見直し、自分達で採用活動を行うことで、採用コストを抑えながら、社内で採用に関する知見・情報を蓄積していくことが可能です。
採用環境は日進月歩で変化をし続けています。働き方改革、コロナウイルス、労働力低下、外国人材の受け入れなど、世の中が大きく変わろうとしている中、今までの当たり前が当たり前ではなくなっています。
その時にどうすべきかといえば、自分達でやりながら、検証と改善を繰り返していくことです。
ぜひ貴社の採用力を高めるきっかけになれば幸いです。